| ★日 本 |
文禄・慶長の役 1592~1598 壬辰倭乱・丁酉再乱 |
大航海物語★ |
| 日本 Nippon | 便郵国帝本日大 | MARSHALL ISLANDS | |||
日本の千石船 韓国 1965/4/20 発行 |
朝鮮半島と日本の地図 昭和5年 1930/9/25 発行 |
亀甲船が豊臣秀吉侵略軍を撃破
|
|
文禄・慶長の役(1592/4~1598/12)は、韓国では「壬辰倭乱・丁酉再乱」と呼ばれています。豊臣秀吉が日本全国を平定して後、その侵略軍が朝鮮に襲いかかり、日本軍と朝鮮・明の援軍との連合軍が戦った戦争です。 |
文禄の役、1592~1593、壬辰倭乱
| 日本 Nippon 日本の千石船  韓国 1965/4/20 発行 |
日本の甲冑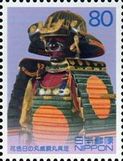 韓国 1965/4/20 発行 |
Republic of China 明のジャンク船  マーシャル 1998 発行 |
|
文禄の役 「壬辰倭乱」(じんしんわらん、イムジンウェラン) (1592年(文禄元年)に始まって翌1593年(文禄2年)に休戦) 文禄元年(1592年)、明の征服と朝鮮の服属を目指して宇喜多秀家を元帥として16万の軍勢を朝鮮に出兵した。初期は朝鮮軍を撃破し、漢城、平壌などを占領するなど圧倒したが、各地の義兵の抵抗や明の援軍の到着によって戦況は膠着状態となり、文禄2年(1593年)、明との間に講和交渉が開始された。 1596(文禄2)年に講和交渉を始め、休戦になりました。 慶長の役 「丁酉再乱」丁酉倭乱(ていゆうわらん、チョンユウェラン) (1597年(慶長2年)講和交渉決裂によって始まり、 1598年(慶長3年)の秀吉の死を受けた日本軍の撤退をもって終結) 文禄5年(1596年)、文禄2年から続いた明との間に講和交渉が決裂し、慶長2年(1597年)、小早川秀秋を元帥として14万人の軍を朝鮮へ再度出兵する。漆川梁海戦で朝鮮水軍を壊滅させると進撃を開始し、2ヶ月で慶尚道、全羅道、忠清道を席捲、京畿道に進出後、南岸に城塞(倭城)を築いて久留の計が取られることとなる。このうち蔚山城は完成前に明・朝鮮軍の攻撃を受け苦戦したが、援軍を得て大破した(第一次蔚山城の戦い)。同年の貴族の日記に、大阪城にいる秀吉のもとに象が連れて来られたと記録されている。 豊臣秀吉が慶長3年(1598年)8月18日、五大老筆頭の徳川家康や秀頼の護り役の前田利家に後事を託して伏見城で没した。 この後朝鮮では、第二次蔚山城の戦い、泗川の戦い、 順天城の戦いで次々と明・朝鮮軍を撃破していた。しかし秀吉の死去にともない朝鮮からの撤兵が決まり、朝鮮出兵は終了した。この戦争は、朝鮮には国土の荒廃と軍民の大きな被害をもたらし、明には莫大な戦費の負担と兵員を損耗によって滅亡の一因となった。 主な戦い 1592(文禄元)年 4月28日 忠州の戦い - 小西行長対申 ? 5月18日 臨津江の戦い - 加藤清正対李陽元 6月5日 龍仁の戦い - 脇坂安治対李洸 7月8日 閑山島海戦 - 脇坂安治対李舜臣 7月8日 梨峙の戦い - 小早川隆景対権慄 7月9日 (第1次)錦山の戦い - 小早川隆景対高敬命 7月17日 (第1次)平壌城の戦い - 小西行長対祖承訓 8月18日 (第2次)錦山の戦い - 小早川隆景、立花宗茂、安国寺恵瓊対趙憲 10月5日 (第一次)晋州城の戦い - 細川忠興、長谷川秀一対金時敏、郭再祐 1593(文禄2)年 1月6日 (第2次)平壌城の戦い - 小西行長対李如松 1月26日 碧蹄館の戦い - 小早川隆景、立花宗茂、宇喜多秀家対李如松、?大受、高?伯 2月12日 幸州山城の戦い - 宇喜多秀家、石田三成対権慄 6月19日 (第二次)晋州城の戦い - 宇喜多秀家、黒田長政、加藤清正対崔慶会、金千鎰 1597(慶長2)年 7月15日 漆川梁海戦 - 藤堂高虎対元均 8月13日 南原城の戦い - 宇喜多秀家対楊元 9月7日 稷山の戦い - 黒田長政対解生 9月17日 鳴梁海戦 - 藤堂高虎対李舜臣 12月21日(翌1月4日まで) 蔚山城の戦い - 加藤清正、毛利秀元、黒田長政、小早川秀秋対楊鎬、麻貴、権慄 1598(慶長3)年 1月2日 般丹の戦い - 立花宗茂対高策 9月18日 順天城の戦い - 小西行長対劉?,陳? 9月22日 (第2次)蔚山城の戦い - 加藤清正、立花宗茂対麻貴 10月1日 泗川城の戦い - 島津義弘対董一元 11月18日 露梁海戦 - 島津義弘、立花宗茂、小早川秀包対陳?、李舜臣、鄧子龍 亀甲船(きっこうせん・きこうせん、???)とは、 李氏朝鮮時代に存在したとされる朝鮮海軍の軍艦の一種。一般に「亀甲船」が通称となっているが、本来は「亀船」とされる。 史書の記録 亀甲船は複数の史書にその存在が記されている軍艦であるが、現存する船体がない事、史書の記述があいまいな事から詳細は明らかではなく、研究の途上にある艦である。太宗実録に初めて記録された[1]。豊臣秀吉による文禄・慶長の役で実際に運用された。 李舜臣行録 「亀甲船の大きさは、板屋船(当時の主力戦艦)とほぼ同じく上を板で覆い、その板の上には十字型の細道が出来ていて、やっと人が通れるようになっていた。そしてそれ以外は、ことごとく刀錐(刀模様のきり)をさして、足を踏み入れる余裕も無かった」、「前方には竜頭を作り、その口下には銃口が、竜尾にもまた銃口があった。左右にはそれぞれ6個の銃口があり、船形が亀のようであったので亀甲船と呼んだ」、「戦闘になると、かや草のむしろを刀錐の上にかぶせてカモフラージュしたので、敵兵がそれとも知らず飛び込むとみな刺さって死んだ。また、敵船が亀甲船を包囲するものなら、左右前後から一斉砲火をやられた」 [編集] 現実の亀甲船 現実の亀甲船は木造船の一種で手漕ぎの突撃艇であると推測され、史書の「李忠武公全書」に装甲艦であると指摘できる記述が存在しない事から装甲艦とは見なされない。 |
| ★日 本 |
慶長の役 1597~1598 丁酉再乱 |
大航海物語★ |
| 日本 Nippon 日本のご朱印船 |
MARSHALL ISLANDS 亀甲船が日本の侵略軍を撃破 |
||
 韓国 1965/4/20 発行 |
李舜臣の亀甲船 |  マーシャル 1998 発行 |
丁酉再乱 |
|
|
|||
| 便郵国帝本日大 朝鮮半島と日本の地図  昭和5年 1930/9/25 発行 |
MARSHALL ISLANDS 明のジャンク船  マーシャル 1998 発行 |
||
▼文禄・慶長の役の海戦、 文禄の役 ▼閑山島海戦(1592~93) 文禄元年(1592年)4月の釜山上陸以来、見るべき抵抗の無かった朝鮮南岸に対し、侵攻作戦こそ無いものの策源地の釜山を中心に番外の所隊が支配領域拡大のために展開をしていた。 これらの部隊の海上移動にあたっていた海運部隊が、李舜臣を中心とする朝鮮水軍の5月と6月の二度の出撃で大きな被害を出していた。 これに対処するために豊臣秀吉は6月23日付けの書状で陸戦や後方輸送に従事していた脇坂安治(動員定数1500人)、九鬼嘉隆(動員定数1500人)、加藤嘉明(動員定数750人)の三大名を招集し朝鮮水軍を討つように命じた。 6月14日に三大名は釜山浦に集結したが、功名に逸った脇坂安治は抜け駆けをして7月7日に巨済島へ単独出撃をした。 一方、二度の出撃で戦果を上げた朝鮮水軍の全羅左水使・李舜臣(24隻)は7月6日に日本水軍の動きを察知すると直ちに出撃し、慶尚右水使・元均(7隻)と全羅右水使・李億祺(25隻)の水軍と合流した。 7月8日、日本水軍を発見した李舜臣は出撃を主張する元均を抑え、囮と潮流を使った迎撃作戦を展開した。 また、この艦隊には亀船三隻が参加されていたという。 囮と海流に乗って出撃した脇坂水軍は有力な朝鮮水軍の迎撃を受け大きな被害を出し、脇坂安治も窮地に陥るが、座乗船の大きさと櫂の数による機動性を生かして撤退に成功した。 李舜臣は自身の記録である乱中日記で、日本水軍の発見数を大船36隻・中船24隻・小船13隻、撃破数を63隻と記録している。 しかし、脇坂安治の動員数が1500人であることを考えると攻撃側から見た発見数と戦果は過大評価だといえよう。(翌年5月の晋州城攻撃時の脇坂軍の点呼員数は900人) とはいえ、この海戦で脇坂安治は、武将の脇坂左兵衛と渡辺七衛門を失い、海賊出身の真鍋左馬允は船を失って上陸後に責任感から切腹しているので大きな被害を受けたことは確かであろう。 また脇坂水軍の内、海戦中に船を放棄して閑山島に上陸した者が200人生還している。 脇坂の抜け駆けを知った九鬼と加藤の水軍は7月6日に釜山出帆、7日に加徳島、8日に安骨浦に停泊して後を追った。 安骨浦に日本水軍が停泊しているとの報告を受けた李舜臣は悪天候で足止めされた後、10日に停泊中の日本水軍を襲撃した。 安骨浦は浅瀬で大型船の運用に危険が伴うため、李舜臣は日本水軍を誘引する作戦を取ったが日本水軍は誘いに乗らなかった。 やむなく順次突入させて大砲を放つ作戦へ変更して朝から晩まで攻撃を繰り返した。 攻撃を受けた日本水軍は夜の内に安骨浦を脱出して帰投し、朝鮮水軍も翌日から根拠地へ帰投した。 李舜臣は自身の記録である乱中日記で日本水軍の発見数を大船21隻・中船15隻・小船6、と記録している。 慶長の役 漆川梁の海戦(巨済島の海戦) 1597年に李舜臣の後任の水軍統制使元均が朝鮮王朝の攻撃命令を嫌がりながら遂行したが、漆川梁海戦(巨済島の海戦)で大敗を喫し、戦死した。 鳴梁の海戦(めいりょうのかいせん) 鳴梁海戦は、鳴梁渡海戦ともいい、慶長の役における海戦の一つ。 慶長二年(1597年)9月16日に陸軍に呼応して西進しようとした日本水軍と朝鮮水軍との間に起こった海戦。 韓国では鳴梁大捷と呼ばれる、李舜臣率いる朝鮮水軍が日本軍に勝利を収めた戦いとして評価が高い。 しかし、日本水軍先鋒を地の利を生かして攻撃した後は衆寡敵せずに撤退しており、戦場の制海権を失ったために基地である(全羅道)右水営や対岸の珍島を攻略を許し、日本水軍の侵攻は成功した。 また、伊予の来島通総が朝鮮の役に出征した唯一の大名戦死者となった。 鳴梁渡は珍島と右水営半島との間にある海峡であり、潮流が速く大きな渦を巻いている航行の難所。 慶長二年(1597年)8月下旬、左軍に属する船手衆の将藤堂高虎、加藤嘉明、脇坂安治、来島通総らは南原城攻略後に艦船に帰り、陸軍に呼応して全羅道の南海岸沿いを西進しようと図った。 先鋒が九月六日に於蘭浦沖に達し、碧波津(珍島の東北端の渡し口)に布陣していた李舜臣率いる朝鮮水軍との間に小競り合いが生じる。 朝鮮水軍はいったん日本水軍先鋒を撃退するが、大船は十二、三隻があるだけだったので、後続の日本水軍の集結を知るとひとまず鳴梁渡に退き、14日さらに右水営沖に移った。 藤堂高虎らは敵大船が近くにいることを知ってその捕獲を図り、9月16日、水路の危険を考えて全軍ではなく中型船四十隻ほど(朝鮮側記録では百三十余隻)で鳴梁渡へ向かったものの、それを察知して迎え撃った大船十二隻、その他百隻の陣容の朝鮮水軍に、来島通総以下十人が戦死、藤堂高虎が負傷、数隻が沈没するなど苦戦した。 夕方になると朝鮮水軍は唐笥島に退き戦闘は終結する。 日本水軍は水路に不案内なため、帆を上げて戦場を離脱する朝鮮水軍を追撃することは適わなかった。 朝鮮側の記録では十三隻が参加し喪失は無し、戦死三十四人という。 露梁の海戦 慶長三年(1598年)11月18日に順天城守備の小西行長らの撤退を支援するために海路出撃した島津軍を中心とした日本軍と明・朝鮮水軍との間に露梁津で起こった海戦であり、朝鮮の役での最後の大規模海戦である。 朝鮮水軍の主将李舜臣はこの戦いで戦死した。 韓国では露梁大捷と呼ばれ朝鮮・明連合水軍が日本軍に大勝した戦いとされる。 露梁津は南海島と半島本土との間の海峡である。 慶長三年(1598年)、日本軍最左翼の要衝である順天城守備の小西行長らは南下してきた明・朝鮮軍の9月19日から10月4日にわたる陸海からの攻撃をいったんは退けたが、豊臣秀吉死去の報を受け釜山へ撤退することとなった。 明・朝鮮水軍が拠点であった古今島へ退いたのをみて、11月10日、船団を仕立てて退去を図るも、やはり秀吉の死亡を知った明・朝鮮水軍に退路を遮断され順天城へ引き返さざるを得なくなった。 既に撤退のため巨済島に集結を終えていた島津義弘、宗義智、立花宗茂(当時の名乗りは統虎)らの左軍諸将はそれを知り、急遽五百隻(三百隻とも言う)の兵船を仕立て、救援のため17日の夜、順天へと向かった。 これを知った明・朝鮮水軍も迎撃するため封鎖を解き露梁津へと東進する。 18日未明、露梁津を抜けようとした日本軍は南海島北西の小島、竹島の陰に潜んだ明水軍と同じく南海島北西の湾、観音浦に潜んだ朝鮮水軍とに出口で待ち伏せされ、南北から挟撃される形で戦闘が始まり乱戦となる。 先陣を切っていた島津軍に損害が大きく、島津の将樺山久高率いる一隊は当初に朝鮮水軍の潜んでいた観音浦に逆に押し込められて浅瀬に座礁して船を失い、徒歩で南海島を横断して対岸へ脱出せざるを得ないという状況も現出した。 主将の島津義弘の座乗船も損害が大きく一時窮地に陥り、他家の救援を得てようやく脱出できたと伝えられる。 このように戦況は日本軍に不利であり、夜が明けるころには大勢は決し、日本側の撤退により戦闘は終結した。 朝鮮側の記録「宣祖実録」には「日本船百隻捕捉、二百隻焼破、斬首五百、捕虜百八十余、溺者数知れず」とある。 だが、李舜臣、明軍の副将鄧子龍といった将官が戦死し、一時突出した明軍の主将陳リンも日本軍の包囲から危うく逃れたとされ、一方的な戦闘展開ではなかったものと考えられる。 海戦後に明・朝鮮水軍が退却する日本軍を追撃したり、あるいは再び順天を封鎖することが適わなかったことからすれば、明・朝鮮軍の損害もまた大きく余力は残っていなかったものであろう。 参考HP:~朝鮮半島の地図 09/2/23 |
スタンプ・メイツ
Copyright(C):Nicky
無断転載禁止